トレーシングレポートとは?流れから書き方を解説!
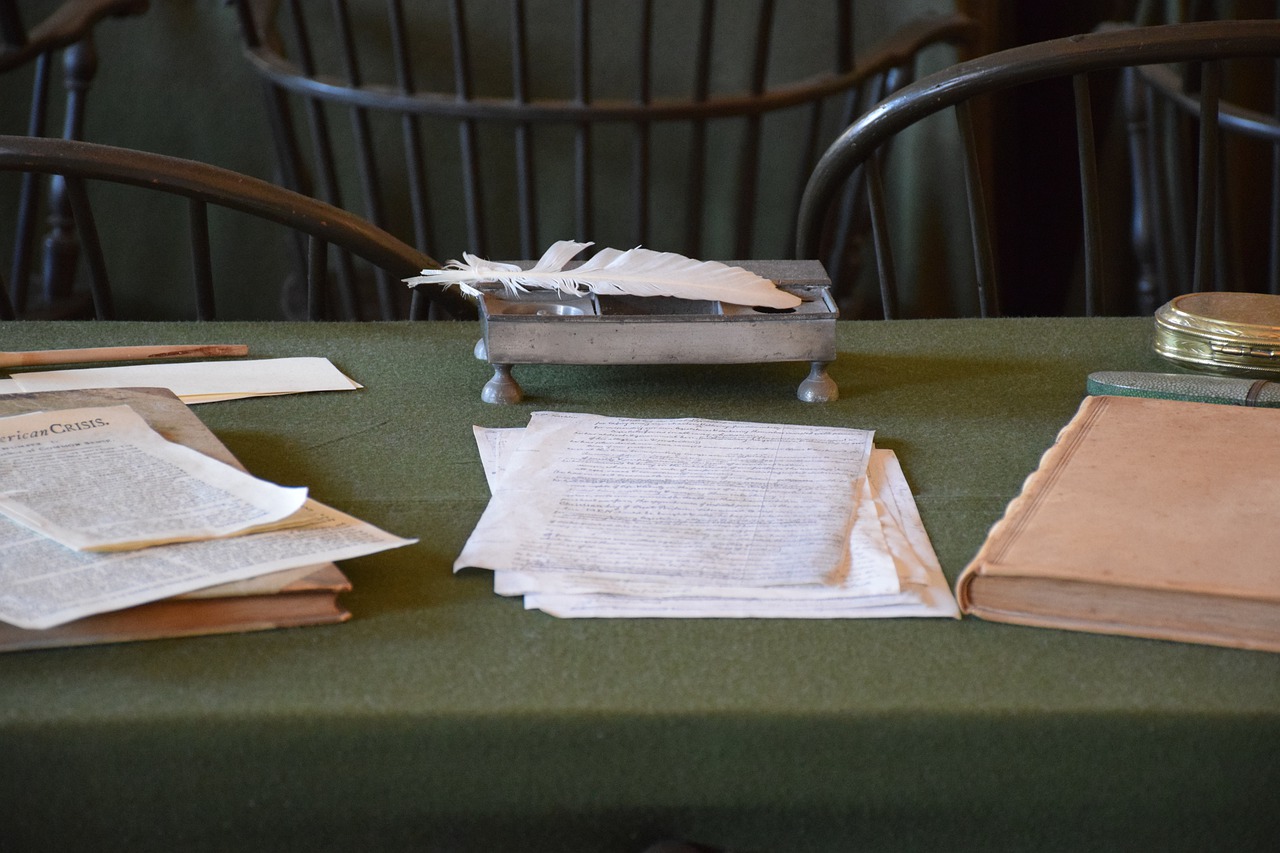
患者さんを見ていくなかで、薬剤師が知った情報を共有するために使うトレーシングレポート。
「服薬情報提供書」とも呼ばれるもので、薬局と医療機関を結びつける大切なものです。
患者さんの治療をよりよいものにしていくためには、トレーシングレポートの活用が欠かせません。
しかし、いざ書こうと思ってもなかなか手が進まないこともあるでしょう。
そこで今回は、トレーシングレポートを書く前の下準備や書き方などを詳しく解説します。
トレーシングレポートはいつごろ始まったのか?
トレーシングレポートが正式に始まったのは2016年です。
それまでは医療機関から求めがあった場合にのみ、情報提供書で算定ができていました。
求めがなければ算定もできないため、あまり情報提供書の作成は行われていなかったのです。
2016年になると、求めがなくても薬剤師の判断でトレーシングレポートを書くことができるようになりました。
算定が取れるようになったことから、積極的にトレーシングレポートを書くようになる薬局が増え始めます。
さらに2018年になると算定方法がさらに細分化されました。
医療機関の求めによって書いた場合は30点、薬剤師の判断で書いた場合は20点を算定できるようになります。
このことから、トレーシングレポートの活用が推進されていることがわかると思います
トレーシングレポートとは?
トレーシングレポートとは、緊急性はないものの次回の診療に役立てるため医療機関に伝えるべき情報をまとめたものです。
薬局で患者さんの対応をしていくうえで知った情報をわかりやすくまとめていきます。
たとえば、「残薬があるので次回の処方で調整してほしい」、「お昼に飲み忘れることが多いので同種同効薬の○○へ変更を検討してほしい」などの情報です。
疑義照会とは違い、即座に対応をお願いするものではありません。
すぐに対応してほしいもの、絶対に対応してもらわないと困るものはトレーシングレポートではなく疑義照会を行います。
また、トレーシングレポートは医師に聞きたいことを質問するツールではないことも注意が必要です。
検査値や今後の治療方針について教えてほしい、などのように情報を聞き出すことには使えません。
トレーシングレポートを書く前の流れは?
トレーシングレポートは、長々と文章を書けばよいというものではありません。
忙しい医師がほとんどであることを考えると、簡潔にわかりやすく情報をまとめることが大切です。
そのためには、書き始める前にある程度の準備をしておく必要があります。
①何を伝えたいのかをハッキリさせる
まず、もっとも伝えたいこと=結論は何かということを明確にしておきましょう。
伝えたいことが定まっていないトレーシングレポートは、読み終わっても結局は何を伝えようとしているのかがわかりません。
これではトレーシングレポートを読んだ医師も「どうすればいいの?」と困ってしまいます。
目的をもって情報を伝達するためには、伝えたいことをハッキリとさせておくことが大切なのです。
②具体的な内容をまとめる
伝えたいことができた背景もわかりやすくまとめる必要があります。
「なんとなくそう感じた」と言うよりも、「患者さんのこういった発言からそのように思った」と伝えるほうが信頼性が増すためです。
どのタイミングで誰がどのような発言をしたのかをわかりやすく書くために、メモか何かに簡単にまとめておくと便利でしょう。
③信頼性の高い情報を探す
「こういう理由から○○に変更をご検討ください」でもNGなわけではありませんが、できれば信頼性の高い情報を添付して書くようにします。
添付文書やインタビューフォーム、厚生労働省が出している資料などを活用して情報の信頼感をアップさせましょう。
そのためには、トレーシングレポートを書き始める前に参考にする情報源を揃えておくことが大切です。
トレーシングレポートの書き方は?
トレーシングレポートは、一定の書式にそって記入していきます。
医療機関が書式を指定していることもあれば、薬局で決まった書式を採用していることもあるでしょう。
もしも、ひな形となる書式が手元にない場合は、厚生労働省が提供している「患者の服薬状況等に係る情報提供書」を使用すると便利です。
①結論を先に書く
結論はできるだけ早めの段階で書いておきましょう。
そうすることで、何を伝えたいものなのかがわかった状態でトレーシングレポートを読み進められるため、医師に読む負担をかけません。
伝えたいことが複数ある場合は、箇条書きを使って簡潔に書くことも有効です。とにかく見やすさ、読みやすさを優先しましょう。
②5W1Hを意識して内容を書く
・誰が(Who)
・いつ(When)
・どこで(Where)
・何を(What)
・なぜ(Why)
・どのように(How)
読んでいてこれらが明確にわかる文章を心がけます。
5W1Hのすべてを入れ込む必要はありませんが、入れられる情報は書くようにしましょう。
文章を書いていると患者さんが言ったことなのか、それとも薬剤師が考えていることなのかがわかりづらくなることが多いため、とくに「誰が」を意識することが大切です。
「薬局の待合室で待ってもらっているとき、患者さんがお腹(下腹部)を押さえながら痛そうにしていた。大丈夫かと声をかけたところお腹が痛いとのこと。痛いのは胃ではなさそうに見えた。」など、状況を明確に書くよう意識しましょう。
③信頼できる情報を添えて薬剤師からの提案を書く
添付文書やインタビューフォーム、厚生労働省のデータなど信頼できる情報を付け加えておくだけで、トレーシングレポートの信頼性はぐっと増します。
「インタビューフォームに半減期は○時間と載っているため…」のように、書くと医師も情報を受け止めてくれやすくなるでしょう。
まとめ
トレーシングレポートとは、医療機関に共有したい緊急性の低い情報を書くものです。
2016年から薬剤師の判断で情報提供書を書いた場合でも算定できるようになりました。
伝えたいことを明確にし、できるだけ文章の頭に結論を入れることで内容がわかりやすくなります。
共有すべき情報が複数ある場合は、箇条書きも活用してください。
添付文書やインタビューフォームなどの情報を使うことでより信頼性の高いトレーシングレポートができあがります。
患者さんの治療を円滑に進めるためにも、トレーシングレポートをうまく活用していきましょう。
===================
監修薬剤師:原 敦子
HYUGA PRIMARY CARE株式会社
===================
【当コラムの掲載内容に関するご注意点】
1.当コラムに掲載されている情報につきましては、事実や根拠に基づく執筆を心がけており、不適切な表現がないか、細心の注意を払っておりますが、その内容の正確性、有効性につき何らかの保証をあたえるものではなく、執筆者個人の見解である場合もございます。あくまで、読者様ご自身のご判断にてお読みいただき、ご参考に頂ければと存じます。
2.当コラムの情報は執筆時点の情報であり、掲載後の状況により、内容に変更が生じる場合がございます。その場合、予告なく当社の判断で変更、更新する場合がございます。
3.前各項の事項により読者様に生じた何らかの損害、損失について、当社は一切の責任も負うものではございませんので、あらかじめ、ご了承ください。






